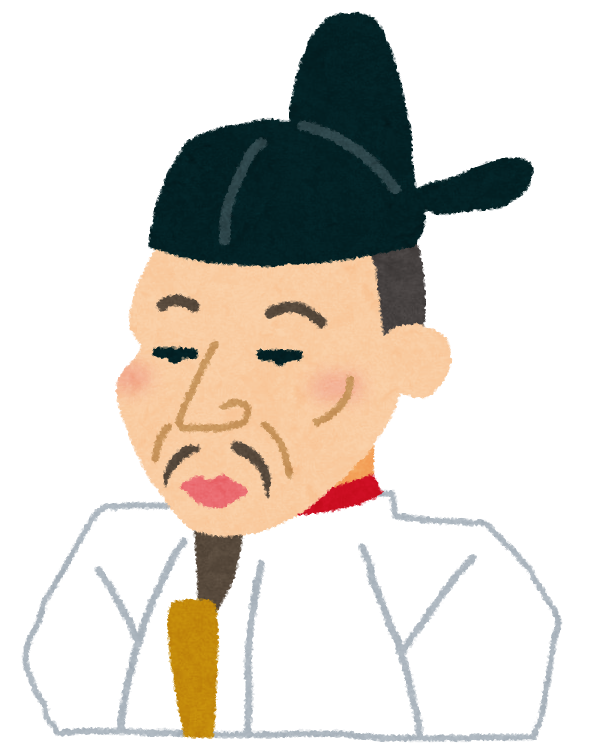すべてを捨てて旅に出た先に何があるか
終わりなき孤独な旅をつづけたある僧の一生
お前はただ札を配れ!
中世、貴賤を問わず道者(仏道の修行者)を集めた熊野は、「この世にあらわれた阿弥陀仏の浄土」とされていた。
『一遍上人絵伝(聖絵)』によれば、熊野本宮大社に向かう山中、一遍はある老僧に出会った。そしてこう語りかけた。
「一念の信を起こして、この名号札を受けとりなさい」
すると老僧は「我には一念の信は起こらない」と拒んだ。
結果、押し問答となり、一遍は名号札を老人に押しつけ、逃げるようにその場を離れたのだった。
ここで一遍は、自分の活動に対する確信が揺らいでしまう。そこで、熊野権現を祀る本宮証誠殿(ほんぐうしょうじょうでん)の宝前にすがるようにぬかずいた。熊野権現は阿弥陀仏の権化とされ、託宣を下す神として知られていたのだ。
果たせるかな、夜半、熊野権現がその姿をあらわし、こう宣べたのである。
「お前のすすめによって、一切の衆生がはじめて往生するわけではない。阿弥陀仏の十劫正覚(じゅうこうしょうかく=はるか昔の成就のとき)に、一切衆生の往生は南無阿弥陀仏が決定しているのだ。お前は信・不信を問わず、浄・不浄にかかわらず、その札を配ればよい――」
まさに、身心脱落、法悦の極みだった。これを機に、彼は名を一遍に改め、名号札に「決定往生六十万人」と追加。「六十万人」には、みずからの歓喜を、阿弥陀仏の福音を、誰かれともなくできる限り伝道しようという意志の表明であろう。のちに時宗では、このときを開宗と定めている。
各地で広がる踊り念仏の輪
一遍は、ついには女房子供をも捨てた。 「智慧をも愚かな疑いをも捨て、善悪の境界をも捨て、貴賤高下の道理をも捨て、地獄をおそれる心をも捨て……一切の事を捨てて唱える念仏」こそ、弥陀の本願にかなう道であると心に刻んで。
貴顕も賤民も関係なく、信心も不信心も問わず、救われの道は平等に開かれている。だから一切の思い計らいを捨て、歓喜のままに念仏を申そう――遊行上人(ゆぎょうしょうにん)とも捨聖(すてひじり)とも称された一遍は、やがて各地で熱狂的な信徒を生み、行く先々で自然発生的に「踊り念仏」の輪が広がっていった。
京の都ではある大臣から、寺領の寄進を受け、一遍とその衆徒のための本山を開き、遊行をやめてはどうかと勧められた。在野の行者といえど、貴顕の庇護を受け、名声と財をなすのは世のなかではよくあること。
だが彼は首を縦に振らなかった。むしろ、名利から逃れるように一遍はまた遊行の旅に出た。
孤独の旅の果ての大いなる救い
一生を旅にたとえれば、最終地点は必ず死である。だが、一遍の旅とは生死を超えるための行であった。生死とは、仏教では「生まれ変わり死に変わる苦しみの世界」をいう。いまだ救いの福音を知らせるべき多くの衆生がいた。そしてみずからも名号に抱かれ、ひとつになりきる旅を完結しなければならない。
愛妻(超一坊)の死は、ひとつの区切りとなった。一度は捨てた女房だが、熊野での成道ののちも、実際は道衆のひとりとして一遍に随従していた。
仏教では古来、女性は業の深き不浄の者として救済の枠外に置かれていたが、一遍は尼僧の同行を許していた。もちろん、男女の過ちは厳に戒めたが、仏道に歩む一遍がそれを恥じなかったのは、女性を救いたいという思いからであった。
〈をのずから相あふ時もわかれても ひとりはいつもひとりなりけり〉
生まれるのもひとり、死ぬのもひとり。愛別離苦は世の習いである。「すべてを捨て、名号に帰一する」とはつまり、大いなる存在とともにある終焉を意味していたであろう。 遺言は「わが亡骸は野に捨てて獣に施すべし」。まさに捨聖の名に恥じぬ最期だった。
- 1
- 2